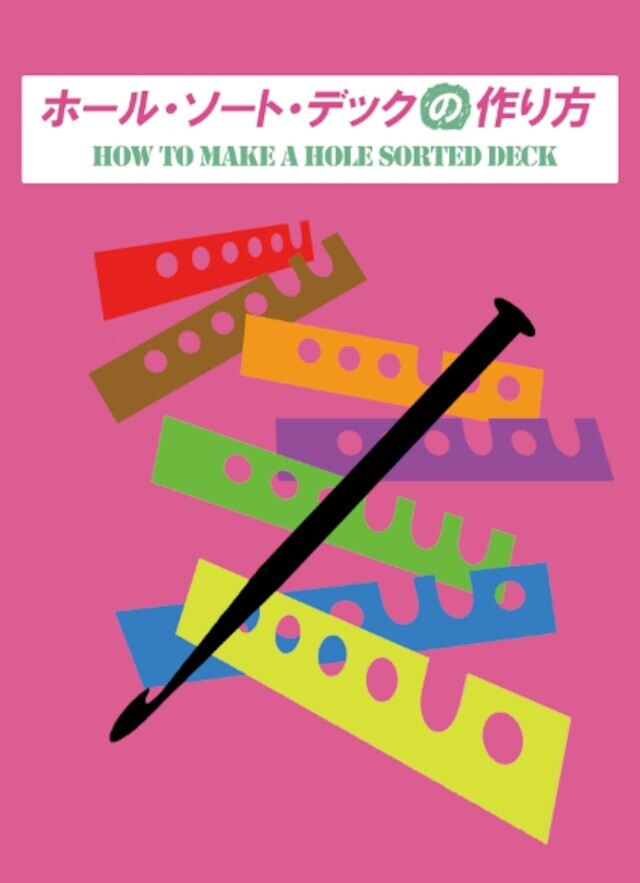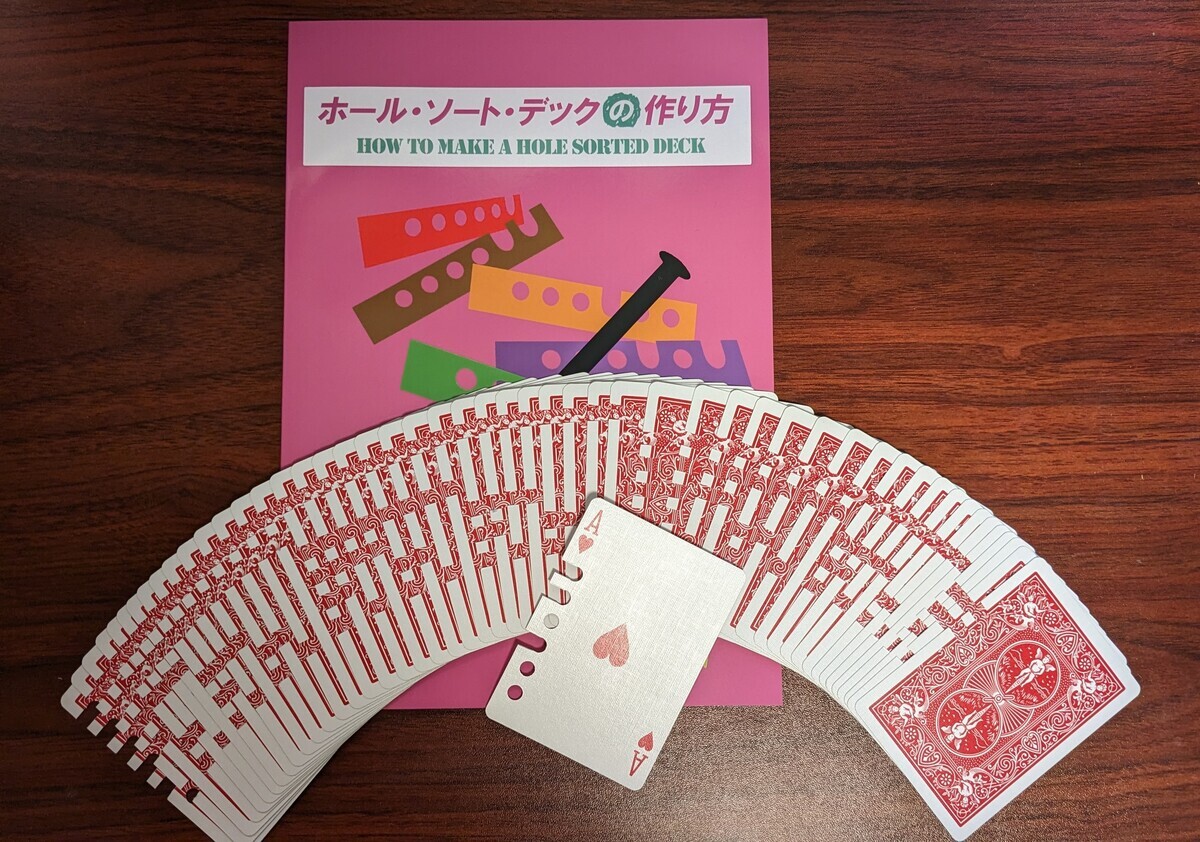先日、我が敬愛するJohn Guastaferroさんの新刊、『Nth Degree』の翻訳・出版権を購入しました。取得しただけでまだ何も受領していないので、諸々は来月以降に始まりますが。新作が読めるのが楽しみです。ていうかGニキ、まずは著者サイン入りの原書を買いたいので早く一般販売してください。
------------
皆さんのお好きなトリックを教えてくださいということで広く募り、ご回答いただいたのが前回2023年末のポストなのですが、いくつか買ったり読んだり触ったりしたものがあるので、備忘録がてらメモ。
1 Dave Campbell, "Thought Anticipated"(『The Dave Campbell Legacy』, Peter Duffie, 2004, p. 155)
→たいへん不思議な手品です。ただ、原書記載の方法・手順より、『monthly Magic Lesson Vol. 96』にてゆうきさんが紹介しているやり方のほうが面倒がなく(とはいえ、最初の準備の手間はあまり変わりませんが)、理屈としても正しいと思いました。繰り返しても演じられますし、手順も複雑ではないので、一度作ってさえしまえば長く使えるとてもいい手品です。
ただ、サークルでも演じた結果、演者としてはラクであるものの、プレゼンテーションがちょっとしっくりこないというか、伝えにくい気がしました。イチ観客として見ると、たしかに不思議なのだけどちょっと反応はしづらいかなあというか。
https://youtu.be/CrrCb0BG6rw?t=1556 萩の月に関する大発見に心惹かれてしまいました笑
2 加藤英夫, "13枚の中の4A" (『第24回 石田天海賞受賞記念 MAGIC 100 マジック・ワンハンドレッド』, 加藤英夫, 1992, p. 26)
あなたは13枚のカードを手に広げて持ち、相手に13枚のうちの好きな枚数目を2つ選ばせます。たとえば相手が3枚目と11枚目といったとします。「私も2つ選びましょう」といって、たとえば2枚目と5枚目を選びます。相手にカードを渡し、1枚ずつ表向きにまかせ、お互いに選んだ2、3、5、11枚目のカードだけ裏向きにまかせます。そして裏向きのカードを表向きにすると、なんと4枚のAなのです。
とこのように現象を書くと、なかなかすごいでしょう。その通りのことを私はできるのですが、問題はそのやり方を説明するのがじつに困難なのです。たとえやり方が理解できたとしても、マスターするのがそれ以上に難しいのです。(中略)いちおう説明いたしますが、これをマスターしようという気は起こされない方がよいかと思います。<本文より>
→著者の記述の通り、ちゃっちゃと練習してすぐにマスターというたぐいの手品ではありませんでした。理屈としては私の好みではあるものの、マスターしようという気は起こさないようにします。しかしこれを勧めてくれた方、「誰も演じてないし、受けも良いので」とのことですが、加藤さん同樣演じられるっぽいので、もうそれだけで凄い。
3 万博, "ゴリラムーブ"(A Bubble Circus(万博), 『すごいぞ!!ゴリラ』, 2019)
→こういうのを読むたび、この人本当に数理の鬼みたいな万博さんと同一人物なのだろうかという疑念がよぎります。万博さんといえば年末ついに新聞沙汰になっていましたね(いい話で)。持っていますし読んでもいますが、実演経験はありません。
4 Matt Sconce, "power word: fall"(Matt Sconce, 『power word: fall』)
→【自分 立てたペン1 立てたペン2 観客】 みたいな位置関係の状態で、ペン2だけが倒れるとかめっちゃ不思議。手も動かさないし、息で倒してもいないしでとても良い。解説がめっちゃ勢いがあって笑ってしまう。いつでもどこでもというとちょっと難しいかもですが、現象は結構薄気味悪いですよねこれ。佳き。
5 Rafael Benatar, "The favorite cards of my friend"(『Simply Impromp2 Vol.3』, Aldo Colombini著, 小林洋介訳, p. 33)
現象:デックをよく混ぜてもらった後に 2 人の観客に好きなカードをたずねます。そしてデックを広げて 演者の好きなカードを見つけだし、観客に渡します。そのカードをデックの中ほどに自由に戻してもらいます。デックを広げて演者の選んだカードを探すと、観客の言った 2 枚のカードの間にあります。
→大正義日本語訳あり。持っていました。サンキュー、ヨースケコバヤシ。今月か来月のサークルで演じてみたいと思います。
6 ドキムーン, "between" (DVD『Brave』, Kimoon Do, 2018, disc1)
→DVD持っていましたし、好きなDVDでもあります。みんな大好きド・キムーン。これはいいですよねえ。最初裏向きで出現したサンドイッチ・カードが一瞬で表向きになるのがかっこいい。キムーンの手品は、あまりごちゃごちゃしていない、そこまで難しくない、結構ビジュアル、という、普通の手品ファンに優しい構成で好き。世の一般的なトランプ手品講師には見習ってほしい。
8 ヒロサカイ, "ノーコントロールインビジブルデック"(フォーサイト, 『ケセラセラ 3』, 2014)
→私、『ケセラセラ』は4しか持っていないの…ですが、なぜかこれは知っているのです。これは枚数目へのコントロール自体はマジシャンが見れば「ああ、なるほど」という感じではあるかもしれないのですが、観客の指定したカードを知る手法が図々しくて好きです。準備不要なのもいいです。
9 Craig Petty, 『Keymaster Chrome』(同名商品)
→買っちゃった。最初にイントロダクションを見たとき、「ペティ随分小綺麗になったなあ」と思ったら、実演や解説をしてくれるのは基本デイヴィッド・ペンでした。途中に、このバージョンの発売時の10年前くらいと思しき頃のペティ本人が映像で出てきますが、まあ今よりマシとはいえ、やはりなんか怖そうな感じで、「そうそう、クレイグ・ペティっていったらこんな感じのむさい人だよな」と思いました。ひとつだけ自分で紙工作が必要ですが、工作ってレベルですらないので良いです。これ用にキーホルダーというかナスカンを買ってきてしまいました。しかしあれです、推薦者の方も言われていますが、カギという普通に穴(キーホルダー用途)が開いていておかしくないものを使い、その穴が塞がったり移動したりする、というのは、日用品マジックとしてきわめて秀逸だと思いました。
14 David Roth, "Eraser coin"(David Roth, 『Expert Coin Magic』, 1985, p. 152)
https://www.youtube.com/watch?v=5BztUahcJG0
→“The Eraser Coin”は初めて動画を見ましたが、まず現象で笑い、「削れる箇所」がコインを持ったときに自然な箇所で、トンデモ手品(※私調べ)なのに手法は真面目、みたいなギャップにやられてしまいました。
15 Paul Curry, "Never in a lifetime" (Paul Curry, 『World Beyond』, 2001, p.298)
→"OotW"が相手の意識的な選択の結果であるのに対し、本作は観客と演者でデックを半分ずつ持ち、観客が混ぜて出来た結果の赤黒の順に応じて演者も同じようにしていくと、観客のパケットと全く同じ赤黒の順になる、というので、まあやはり少し意味合いが違う気がします。ていうかこれ、評判良くないのですか?面白いし、"OotW"の仕組みを知っている相手にも通用しそうな気がします。
フェザータッチマジックの本書に付属する日本語訳は基本抄訳ですが、本作については平賀さんの全訳が付いておりさっと理解できました。やはり日本語はいいですね笑
28 Dan Paulus, "Blind Luck"(同名動画商品)
→悔しいが(推薦者がお友達だったので)大変不思議なトリックだった。Dave Campbellの"Thought Anticipated"と、観客が現象自体から受ける印象は類似していると思いますが、こちらの方が最初に演じるまでのハードルは低い。あっちのほうが公明正大さは高いけれども。とにかくこちらはこちらで傑作というか、本当によくできた作品だなと思いました。
30 桂川新平, "estimation etude"(『Secret Vol. 3 桂川新平』, |Shimpei Katsuragawa著, Ben Daggers訳・編, 『LA CAMPANELLA』, The Impossible Co., 2022, p. 14)
→久々に見ましたけど本当にピンキーカウントが上手いな桂川さん。桂川さんがやってるのを見るとめちゃめちゃ簡単そうに見えるが、実際にやってみると指が生まれたての子鹿みたいになってしまう。できればたいへんかっこよく、現象もスッキリわかりやすい。問題は私にはこんな華麗にできないところです。
32 岡野将太, "Blind"(岡野将太, 『Puzzle』, 2014)
→5人以上くらいでやると、(1人を除いて)めちゃめちゃ盛り上がりますなあ。確かに、一度きりしか演じられないのが惜しい。でもこういう手品は本当に盛り上がる。